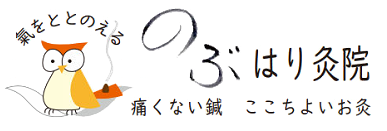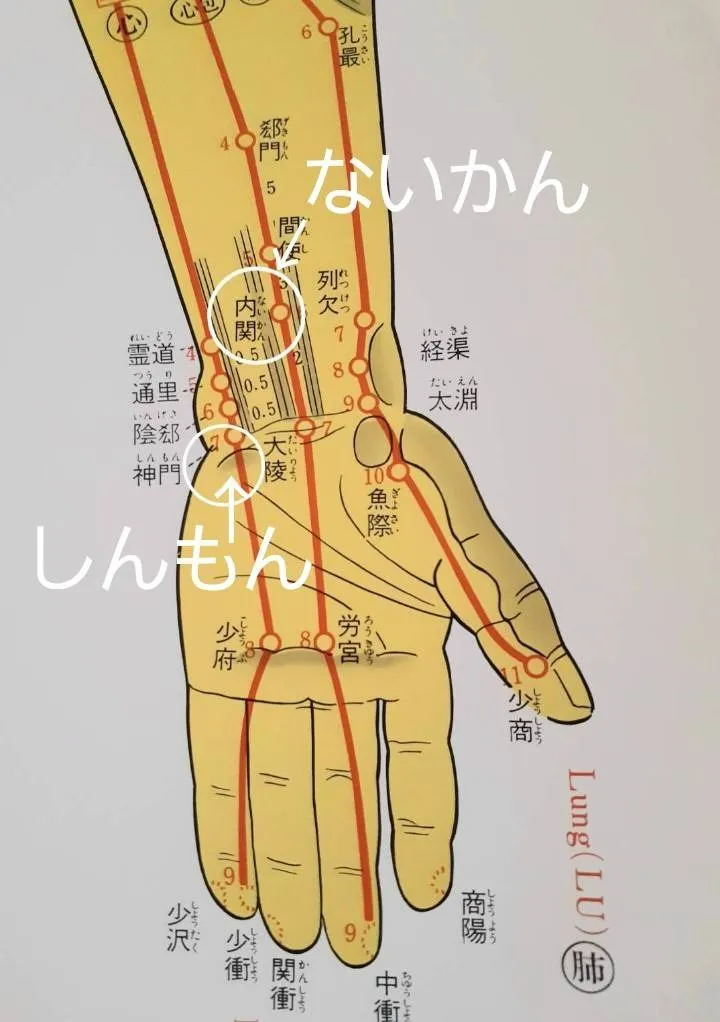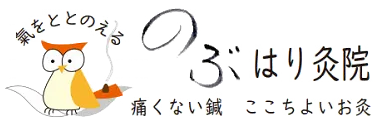現代医学からの冷え
2025/03/24
「冷え(冷え症)」って何?
☆自分の身体が冷えていると感じている。
☆手や足の末梢部分、あるいは上腕部、大腿部などが温まらず、冷えを感じる。
☆暖かい環境にいても、冷えた身体が温まりにくい。
など、冷えているような感覚が常に自覚される状態のことです。
「冷え」はもともと東洋医学特有の概念です。東洋医学では、病気ではないものの、何だか不調を抱え健康といえない状態を「未病」といい、冷えはその代表的な症状の一つです。東洋医学にとって身体の不調はできるだけ未病のうちに改善し病気を防ごうとします。冷えは身体からの黄色信号です。
現代医学では冷えは病態として統一的な定義は確立されていないから漠然とした概念とされています。(しかし、西洋医学の定義を明確にしようとする動きもあるようです。)
「冷えはなぜ起きるのか」
〇血流量の低下が原因の一つ
現代医学では冷えの主な原因は自律神経の失調による血流量の低下からきていると考えられています。
私たちの身体には、「恒常性(ホメオスタシス)」といわれる、身体が変化を嫌い一定の状態を維持しようとする働きがあります。自律神経系や免疫系、ホルモンを生成する内分泌系が関わり、生物の体内環境を一定に保とうとする性質です。
その中で自律神経が全身に熱を運ぶ血管の拡張・収縮活動を調節しています。
自律神経には、興奮時や緊張時に優位になる「交感神経」と、睡眠時やリラックス時に優位になる「副交感神経」があります。
いつもは、この二つがバランスを取りながら身体の恒常性(ホメオスタシス)を保っています。
しかし、ストレスや生活習慣の乱れなどによる理由で交感神経の緊張が続くと血管が収縮し、体内の血液循環が悪くなり、身体のすみずみまで熱が届かなくなってしまい、こうして血液が届きにくい手先や足先などの末端部分に特に冷えを感じやすくなります。
〇その他の冷えを引き起こす要因として
◦食事量・栄養量の不足により体内に熱を保てなくなる。
食事を取ると体内に熱(エネルギー)が生まれますが、ダイエットや偏食などにより食事量が減ったり、偏ったりすることによりタンパク質やミネラル、ビタミンなど、身体の機能を維持するのに不可欠な栄養素が不足すると、身体に熱を保てなくなります。
◦筋肉量の不足により基礎代謝量が低下し、身体が熱を生みにくくなる。
筋肉には身体の熱をつくったり、伸び縮みして血管に圧力をかけ血液の循環を促し体中に熱を運ぶ役割があるからです。
◦運動が足りないと身体が冷えやすくなる。
運動をすると、血行が促進され、筋肉も使われるので身体に熱が発生し、体温が上がります。
◦内分泌機能の不全
痩せすぎや更年期などの理由により、内分泌機能の働きが悪くなり、女性ホルモンの分泌量が低下したり、ホルモンのバランスが崩れたりすると、体温を上昇させる働きがあるプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌がわるくなります。
〇間接的な要因として
◦生活リズムの乱れ
◦心理的なストレス
◦痩せすぎなども影響します。
一つでも当てはまることがあるようでしたら、できる範囲での改善をしてみるのも楽しい明日への一歩になるかと思います(^^♪
以上現代医学からでした。
----------------------------------------------------------------------
のぶ はり灸院
住所 : 大阪府大阪市住吉区大領3-8-29
電話番号 : 090-2654-9491
長居にて冷えの予防とケア
----------------------------------------------------------------------